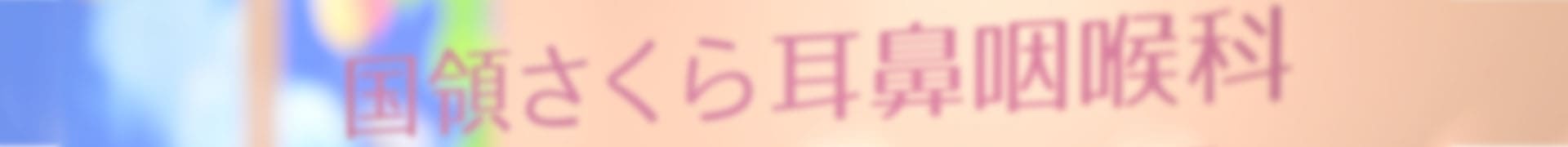
めまい
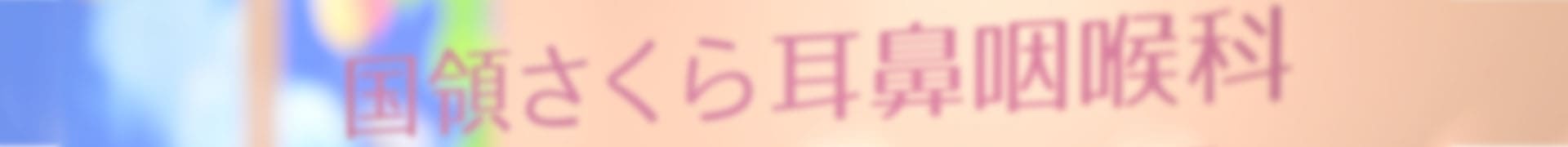
めまい

当院では、「最近ふらふらする」「立ち上がるとクラッとする」「視界が回るような感覚がある」など、日常生活でよく見られる“めまい”の症状について専門的に診療いたします。めまいは、多くの方が経験する症状ですが、原因は人によってさまざまで、耳や内耳の問題、ストレス、年齢による変化、血圧や貧血の影響などさまざまです。丁寧に原因を探り、生活の中での不安を軽くするお手伝いをしています。
まず、「どんなときにめまいが起こるか」「どういう感じのめまいか」を詳しくお聞きします。例えば「立ち上がったとき」「疲れているとき」「回る感じか、ふわふわする感じか」など、日常生活の中でめまいが起きやすいタイミングを伺い、原因を探るヒントにします。
めまいは耳や内耳の問題が原因で起こることが多いため、耳の聞こえ方やバランス機能のチェックを行います。耳鳴りや難聴がある場合にも、耳鼻科的な検査で原因を詳しく調べることができます。
めまいが起きると、眼球が不随意に動くことがあるため、その動きからめまいの原因を調べます。専用のゴーグルをつけて、眼球の動き方を確認することで、内耳や脳の異常がわかることがあります。
重心動揺検査は、「立っている時に体がどれくらい揺れているか」を測定する検査です。普段、意識していないかもしれませんが、バランスをとるために体は常に微妙に動いています。この動きが異常だと、内耳や脳のバランス機能に問題がある可能性が考えられます。台の上に立っていただき、数分間静止している間に体の揺れを記録することで、バランスの状態を詳しく調べます。
めまいは血圧や貧血、栄養バランスの乱れが原因になることもあります。血液検査で鉄分やビタミンの状態を確認し、生活改善が必要かどうかを判断します。血圧の変動が激しい場合は、日常生活での注意点についてアドバイスも行います。
もし脳や神経の異常が疑われる場合には、MRIやCTを使って脳の状態を確認します。特に脳卒中や腫瘍などの可能性を調べるため、安心して診療を進められるようにしています。画像診断に関しては近隣の慈恵医大第三病院連携して当院にて予約できる体制を整えております。
検査の結果によって、めまいの原因がわかれば、症状に合わせた治療やリハビリプランを作成します。耳や内耳が原因の場合は薬やリハビリが有効で、バランスをとるための簡単な体操なども指導しています。また、栄養バランスや生活習慣の改善も一緒にサポートし、日々の生活が楽になるようお手伝いします。
めまいは再発しやすい症状でもあるため、定期的に状態をチェックしながら、リハビリや生活アドバイスを続けていきます。例えば、日常生活で気をつけるべきことや、症状が悪化しそうなときに役立つケア方法などもお伝えし、安心して生活が送れるようにサポートします。
めまい外来では、患者さんが「めまいと上手に付き合いながら日常生活を送れるように」お手伝いをしています。「ただの疲れだろう」と思わず、少しでも不安がある場合はお気軽にご相談ください。
めまいとは自分の姿勢や動きをしっかりと認識できなくなった状態(平衡失調・空間識失調)です。めまい症状があった時に実際にそういった眩暈なのか、耳のその他の病気に伴うものなのか、脳梗塞や全身的な体調不良・筋力の低下などに伴うものなのかどうかという判断は受診していただいてから行うため、症状があった場合にはご遠慮なく受診ください。
めまいは厳密には目が勝手にある一定方向に動いている(眼振)を伴いますので、眼振がないか赤外線カメラで実際に目の動きを観察します。さらに、脳梗塞などの兆候がないか、目を閉じて立ってもらったり、歩いていただいたりします。頻繁に聴力低下を伴うことがあるため、必要であれば聴力検査も行います。
メニエール病は、ぐるぐると周囲が回るように感じる「めまい」と、耳鳴り、難聴、耳の閉塞感や吐き気などの症状を、発作的に繰り返す病気です。発作は30分から数時間に及ぶ場合もあります。耳鳴りや難聴などの聞こえの症状は、発作を起こしてから次第に軽くなりますが、めまいは悪くなる場合があります。めまいは、突然発症する、持続する、寝ても座っても回り続ける、といった特徴を持っています。
内耳の中に、内リンパ水腫ができることが原因とされていますが、その根本的な原因は、まだ解明されていません。睡眠不足や過労、ストレスなどが背景にある、との説もあります。検査では、聴力検査や目の不規則な動きを調べる眼振検査が行われます。めまい止めや利尿薬などで治療を行いますが、一度良くなってもストレスや不眠などで再発をします。このため、普段からの体調管理も再発防止に重要になります。
朝起き上がる時、起き上がってからちょっとしてぐるぐる目が回って立っていられず、数分間待っていたら症状が良くなったが、また同じことを繰り返すと目が回るというのが典型的な症状です。頭をぶつけた後などにも、同じ方向に頭を動かすと目が回るというのも良く見受けます。耳鳴りや聴力低下を伴わず、頭を動かすことにより誘発される眩暈(めまい)がこの病気の特徴です。まずは受診し、赤外線カメラでめまいが起きる頭の動きを行い、目の揺れ(眼振)が誘発されることを確認します。治療は、めまい症状が強いうちはめまい止めや吐き気止めの内服となりますが、リハビリ療法も重要となるため指導いたします。
風邪などを引いた後、1週間ぐらいしてからぐるぐる目が回って立っていられないというのが典型的な症状です。しかし、風邪など先行する感染などの認識がない場合も多々あります。耳鳴りや聴力低下、その他の麻痺症状などは無く、ひたすら目が回るというのが特徴です。
まずは、受診して赤外線カメラで目の揺れ(眼振)を確認します。また、脳の病気のサインは無いかもチェックします。治療は、めまい症状が強いうちは吐き気止め、めまい止めの内服となりますが、この病気はふらつきが月単位で続くことが多く、リハビリも重要となります。めまいの激しい初期には、安静抗ヒスタミン薬・抗不安薬・副腎皮質ホルモンも有効です。症状は数日間で徐々に減退し、2~3週間後に頭部運動に際するめまい感を残して軽快に向かいます。