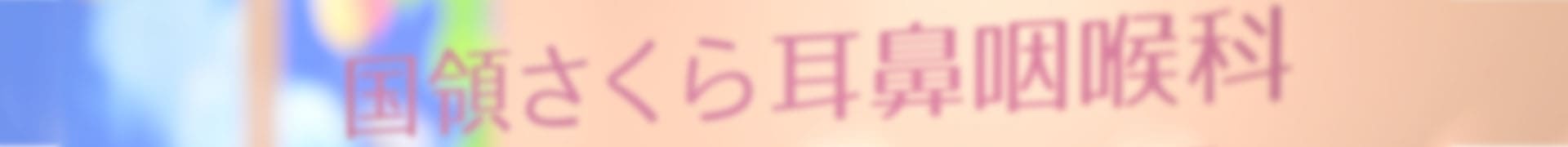
子どもがかかりやすい病気
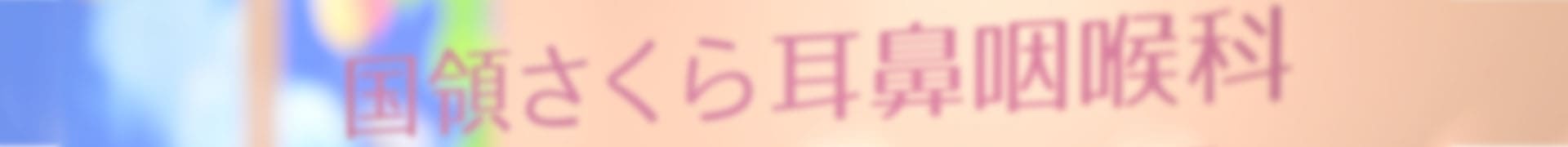
子どもがかかりやすい病気

お子様が遊んでいる最中に、ビーズや消しゴムなどを耳に入れてしまうことがあります。自分で取り除こうとすると、耳の中や鼓膜を傷つける恐れがあるため、速やかに受診して専用の器具で安全に除去することが重要です。
一般的に「耳あか」と呼ばれるものです。お子様の場合、耳の穴が狭く、耳垢が取りづらいことがあります。無理に取ろうとせず、お困りの際はご相談ください。専用の器具で丁寧に除去します。硬い耳垢で一度で取れない場合は、耳垢を溶かす薬を使うなどの専門的な方法で対応します。
耳の前方上部に小さな穴が見られることがあります。この穴は皮膚の下に1~2cmほど続いており、垢のようなものが溜まって感染を引き起こす場合があります。抗生剤の内服だけでは改善しないことが多く、膿を出すための処置が必要になることもあります。繰り返す場合は、手術治療が必要となることもあり、専門医への紹介が行われます。
突然の耳の痛みや発熱が主な症状です。すべての年代で発症しますが、特に幼少期に多く見られる病気です。痛みを言葉で伝えられない小さなお子様では、急な発熱や不機嫌、耳を触るなどの行動が見られます。鼻風邪(急性鼻炎)から耳に感染が広がることが原因で、基本的には内服と鼻炎の治療で回復しますが、繰り返すことで滲出性中耳炎に進行する場合があります。
当院の滲出性中耳炎外来では、子どもに多く見られる滲出性中耳炎に対し、丁寧な診断と治療を行っています。この病気は、耳の奥に液体が溜まることで聞こえが悪くなる状態を指し、放置すると聴力や言語発達に影響を与える可能性があります。そのため、早期の発見と適切な治療が大切です。当院では、豊富な経験と知識を持つ医師が、患者さんの症状や状態に応じて最適なケアを提供し、安心して治療を受けていただけるよう努めております。
当院の滲出性中耳炎外来では、次のようなプロセスで患者さん一人ひとりに合った診断・治療を行います。
まず、患者さんの症状をしっかりとお伺いし、適切な診断のための検査を行います。
検査結果に基づき、患者さん一人ひとりの状態に応じた治療方針を慎重に検討し、最適な治療法をご提案します。
滲出性中耳炎の治療と再発予防のために、日常生活での注意点やケアについてもお伝えいたします。
当院の滲出性中耳炎外来では、首や耳、鼻の病気に関する十分な知識を持った医師が診療にあたります。小さなお子様の聴覚や言語の発達に関わる大切な疾患ですので、患者さんとそのご家族が安心して治療を受けられるよう、丁寧に説明しながら進めてまいります。また、当院では早期発見と治療が可能な体制を整え、患者さんが快適に治療を継続できるよう万全のサポートを提供いたします。
「耳が聞こえにくい」「耳が詰まった感じがする」など、少しでも気になる症状がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。早期の診断と適切な治療によって、滲出性中耳炎による影響を最小限に抑えることができます。お子様の健康と成長を支えるため、当院は常に患者さんとご家族に寄り添いながらサポートを提供いたします。
突然の「くしゃみ、鼻水、鼻づまり」、いわゆる鼻風邪の症状です。治療は鼻水を抑える薬や炎症を抑える内服薬を使用します。粘り気のある黄色い鼻水が出る場合は細菌感染が疑われ、中耳炎のリスクもあるため抗生剤を使うことがあります。また、ネブライザー治療を併用することで、薬を鼻の奥まで行き渡らせ、症状の早期改善が期待できます。
くしゃみ、鼻水、鼻づまりが典型的な症状で、患者数は年々増加しています。スギ花粉症がよく知られていますが、ダニやほこりによる通年性アレルギーも多く見られます。小児の場合、症状が軽いことが多く、常に鼻が詰まっている状態やいびきをかく原因となることがあります。まずは血液検査や鼻汁の好酸球検査を行い、アレルギー性鼻炎かどうか、そして原因が何であるかを確認します。年齢に応じて飲み薬や点鼻薬、10歳以上の場合はレーザー治療も選択肢となります。通年で症状が続く場合は、舌下免疫療法でアレルギーの改善を目指すことも可能です。
急性鼻炎が悪化し、顔の両頬やおでこにある副鼻腔まで炎症が広がった状態です。膿状の鼻水がたまり、鼻づまり、頭痛、頬の痛みなどの症状が現れます。小児は鼻の構造が未発達のため、大人に比べて副鼻腔炎になりやすい傾向がありますが、抗生剤などで迅速に治療すれば、慢性副鼻腔炎に移行することはほとんどありません。
一般的に「蓄膿症」と呼ばれるもので、悪臭を伴う鼻水や鼻づまり、喉に痰が溜まる感覚、嗅覚の低下が主な症状です。急性副鼻腔炎が治りきらず長引いた場合や、アレルギー性鼻炎で鼻の粘膜が腫れたことで、副鼻腔に膿が溜まってしまうことが原因です。小児では、主に細菌感染が原因であるため、レントゲンやCT検査で副鼻腔の状態を確認し、必要に応じて治療を行います。重症の場合は、マクロライド療法という大人と同様の治療法を採用します。
小児の鼻血は、ほとんどが鼻中隔の手前にあるキーセルバッハという部位から出血しています。出血があった場合は、綿やティッシュを鼻に詰め、鼻の外側から圧迫して止血します。頻繁に鼻血が出る場合は、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎が原因で鼻を触りやすい状態になっていることが多く、鼻炎治療で改善するケースが少なくありません。
主な症状は、小児の発熱とのどの痛みです。のどの痛みはウイルス性の風邪が多いですが、細菌による場合は溶連菌感染が疑われます。この感染症は、時に心臓の弁や腎臓に合併症を引き起こすことがあるため、正確な診断と適切な治療が重要です。当院では、当日結果が分かる検査が可能です。治療は主に抗生物質の服用で、多くの場合迅速に改善します。治療後は、一度尿検査を行うことをお勧めします。
のどの痛み、目の充血、発熱が3大症状であり、夏風邪とも呼ばれます。ウイルス性のため、完治までに約1週間かかります。症状を和らげるために、必要に応じてお薬を処方します。この感染症は非常に伝染しやすいため、早期診断が重要です。当院では、当日中に結果が分かる検査が可能です。症状が治まり2日経過するまで、出席停止となります。
扁桃腺(口蓋垂の両脇)や、鼻の奥にあるアデノイド(咽頭扁桃)が大きくなり、鼻やのどの空気の通り道が狭くなった状態です。これが原因で鼻づまりや滲出性中耳炎、いびき、無呼吸が引き起こされます。特に3歳頃から大きくなり始め、6~7歳で空気の通り道に対して最も大きくなります。滲出性中耳炎を繰り返す場合、ご飯が食べづらく成長が悪い場合、夜間に呼吸が止まるなどの症状がある場合には、手術による摘出が必要となることがあります。無呼吸やいびきを確認するため、スマートフォンなどで睡眠中の状態を撮影し、診察時に持参いただけると診断に役立ちます。
主に幼稚園年長から学童期に多く見られ、耳の前から下にかけての片側または両側が腫れ、発熱や痛みが症状として現れます。ムンプスウイルスが原因で、感染力が強いため、最低でも5日間は通学が禁止されます。まれに聴力障害や髄膜炎を引き起こすことがあり、成人が感染した場合、睾丸炎、卵巣炎、膵炎といった重症合併症を引き起こすことが知られています。
ワクチン接種で予防は可能ですが、100%の防止は難しく、感染した場合でも症状を軽減できるとされています。治療は基本的に耳下腺の腫れや発熱が治まるまで自宅での安静が推奨されます。